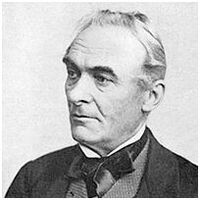2014年07月18日
F/星の王子さまの実像を求めて<3>
アンドレ・ジッドとサン=テグジュペリ
アフリカの蜃気楼に誘われて

改めてサン=テグジュペリの作品を読み直す機会のなかで、ハッと気づいたことがある。それは、野生の大地、いや、不毛の大地のアフリカが、偉大な文学を生む豊穣な母体になっているということ。
神秘と底知れぬ危険を孕んで渺々と広がる砂漠。その恐るべき沈黙と静寂。夢かとまごうあの蜃気楼は幻想の深みへといざない、人にまったく新しいものの見方、考え方を教えてくれるものらしい、ということ。わけても、伸ばせば手が届くかに見える星空の下に目路のかぎり横たわる、まだ人間の足が踏んだこともない沈黙の砂の原は、作家の感性に鮮烈なインスピレーションを与えずにおかないものらしいということ。サン=テグジュペリがそのインスピレーションをそこでつかんだ一人なら、アンドレ・ジッドもまたその一人で、ふたりともアフリカの野生、アフリカの沈黙によって文学的開眼を果たした、と言っても過言でないように思えてきた。
小説家サン=テグジュペリの名をあらしめたのが、彼自身の実体験にもとづいて書かれたサハラ砂漠に不時着した飛行士の物語『南方郵便機』であり、以降『夜間飛行』『人間の土地』から『星の王子さま』に至るまでの名作を生む源泉がそこにあることを疑う人はまずいないだろう。奇遇というべきか、その『南方郵便機』に序文を寄せているがアンドレ・ジッドある。30歳もの年齢差はあるにせよ、このふたりの因縁を辿ってみると、サン=テグジュペリの母の従姉妹にあたるイヴォンヌ・ド・レストランシェが、ジッドの友人であり第二次世界大戦中は母マリーの住むサン・モリス城から遠くないプロヴァンスの小さな村の別荘に疎開していて、マリーとも親交があった。そうした関係から、ときどきこのふたりの作家は顔を合わせ、チェスなどを楽しんだほか、文学的に影響を与え合う関係にはなかったにせよ、よく文学をめぐってはげしい議論を交わし合い、互いに譲り合うことなく、ときには意見の食い違いから仲たがいをしたこともあったようだ。
ジッドは、晩年、アンドレ・マルローやサン=テグジュペリを「今世紀(20世紀)最高の頭脳」と記して敬意と友情をあらわしている。これはしかし、老いてからだのきかなくなったジッド゙が、行動派人間に対しておくる羨望の辞であり、追従でもあったのではなかろうか。
ふたりの関係でもうひとつ重要なのは、『人間の土地』の生まれるきっかけをつくったのがジッドだということ。『夜間飛行』の成功にもかかわらず、パイロット仲間からの中傷を浴びてからというもの、サン=テグジュペリはすっかり小説を書く意欲を喪っていた。そんな彼に、コンラッドの『海の鏡』にならって、これまで各方面の新聞や雑誌に書いてきた飛行にかかわる話を集め、「花束のように」一冊にまとめたらいいんじゃないか、とサジェスチョンしているのがジッドである。
アンドレ・ジッド(1868〜1951)について、もう少し触れてみよう。もっとも多感な17〜18歳のころ、級友のピエール・ルイスを介してポール・ヴァレリーやマラルメ、ヴェルコールといった象徴派詩人を知って文学の道に足を踏み入れた。踏み入れてはみたものの、しばらくはどう努力しても作品が書けなかった。23〜24歳のとき、同窓の友人、ポール=アルベール・ローランスという画家とアルジェリアを旅し、そのアフリカの大地で人間の野生というものに触れた。これが一大転機となって『パリュード』を書いて、思いがけぬ成功をおさめた。これは、理知に疲れたパリの世紀末の空気、生命感をなくした大都会に対する倦怠と嫌悪を、皮肉と風刺をこめて書いたもので、ジッドを初めて“作家ジッド”とした著作だった。それは、ジッドの前を覆っていた黒い帳をパッと切り落とすものであったと同時に、それまでの象徴派詩人たちとの訣別でもあった。
『パリュード』につづいて矢継ぎ早やに作品が書かれ、『地の糧』もまた、神秘と野生に満ちたアフリカの大地への情熱的な讃歌、生命感の讃仰であり、これが彼の創作のエネルギー源となって、以降、『背徳者』『狭き門』『イザベル』『法王庁の抜け穴』『一粒の麦もし死なずば』『田園交響楽』など、よく知られる世界的な名作を次つぎに生み出していった。壮年期に至っては、社会的な問題、政治的な問題に対する発言も多くなり、旅行記『コンゴ紀行』では、ヨーロッパ列強の野心、資本主義的帝国主義の巨大な機構に鵜呑みにされ、無惨に踏みしだかれていくアフリカ植民地の姿をリアリスティックに描いて、その非道ぶりを正面から告発している。
サン=テグジュペリが『星の王子さま』を献じているレオン・ヴェルト(1878〜1955)は、反ファッシズム同盟の会長をつとめていたユダヤ人作家であり美術評論家でもあったが、植民地主義批判を中心とする反戦思想家。当時、大旋風を巻き起こした彼のスターリン批判は、じつはジッドの『ソビエト紀行』のスターリン独裁制批判の思想に依拠し、それを敷衍したもので、ジッドに多大な影響を受けていたことが知れる。
1944年7月31日、44歳という若さではるかな空の巡礼に旅だっていった“星の王子さま”に、74歳の大作家がどんな追悼の辞を述べたのか、わたしは知らない。これも歴史的な運命というべきか、その日からわずかのち、8月25日にはナチス・ドイツの占領下にあったパリは解放された。
若いときから貴族社会の保守反動思想を棄て、カトリックの信仰と王党主義に替わる新しい思想、新しい生き方を求めつづけた男。信念に忠実に生き、良心の命ずるところへ向けてまっすぐ行動した男。その存在はいまも異彩を放って人びとの胸のなかに輝きつづけている。

*「丘の上文庫だより」第45号別刷所収 口演記録より
アフリカの蜃気楼に誘われて

改めてサン=テグジュペリの作品を読み直す機会のなかで、ハッと気づいたことがある。それは、野生の大地、いや、不毛の大地のアフリカが、偉大な文学を生む豊穣な母体になっているということ。
神秘と底知れぬ危険を孕んで渺々と広がる砂漠。その恐るべき沈黙と静寂。夢かとまごうあの蜃気楼は幻想の深みへといざない、人にまったく新しいものの見方、考え方を教えてくれるものらしい、ということ。わけても、伸ばせば手が届くかに見える星空の下に目路のかぎり横たわる、まだ人間の足が踏んだこともない沈黙の砂の原は、作家の感性に鮮烈なインスピレーションを与えずにおかないものらしいということ。サン=テグジュペリがそのインスピレーションをそこでつかんだ一人なら、アンドレ・ジッドもまたその一人で、ふたりともアフリカの野生、アフリカの沈黙によって文学的開眼を果たした、と言っても過言でないように思えてきた。
小説家サン=テグジュペリの名をあらしめたのが、彼自身の実体験にもとづいて書かれたサハラ砂漠に不時着した飛行士の物語『南方郵便機』であり、以降『夜間飛行』『人間の土地』から『星の王子さま』に至るまでの名作を生む源泉がそこにあることを疑う人はまずいないだろう。奇遇というべきか、その『南方郵便機』に序文を寄せているがアンドレ・ジッドある。30歳もの年齢差はあるにせよ、このふたりの因縁を辿ってみると、サン=テグジュペリの母の従姉妹にあたるイヴォンヌ・ド・レストランシェが、ジッドの友人であり第二次世界大戦中は母マリーの住むサン・モリス城から遠くないプロヴァンスの小さな村の別荘に疎開していて、マリーとも親交があった。そうした関係から、ときどきこのふたりの作家は顔を合わせ、チェスなどを楽しんだほか、文学的に影響を与え合う関係にはなかったにせよ、よく文学をめぐってはげしい議論を交わし合い、互いに譲り合うことなく、ときには意見の食い違いから仲たがいをしたこともあったようだ。
ジッドは、晩年、アンドレ・マルローやサン=テグジュペリを「今世紀(20世紀)最高の頭脳」と記して敬意と友情をあらわしている。これはしかし、老いてからだのきかなくなったジッド゙が、行動派人間に対しておくる羨望の辞であり、追従でもあったのではなかろうか。
ふたりの関係でもうひとつ重要なのは、『人間の土地』の生まれるきっかけをつくったのがジッドだということ。『夜間飛行』の成功にもかかわらず、パイロット仲間からの中傷を浴びてからというもの、サン=テグジュペリはすっかり小説を書く意欲を喪っていた。そんな彼に、コンラッドの『海の鏡』にならって、これまで各方面の新聞や雑誌に書いてきた飛行にかかわる話を集め、「花束のように」一冊にまとめたらいいんじゃないか、とサジェスチョンしているのがジッドである。
アンドレ・ジッド(1868〜1951)について、もう少し触れてみよう。もっとも多感な17〜18歳のころ、級友のピエール・ルイスを介してポール・ヴァレリーやマラルメ、ヴェルコールといった象徴派詩人を知って文学の道に足を踏み入れた。踏み入れてはみたものの、しばらくはどう努力しても作品が書けなかった。23〜24歳のとき、同窓の友人、ポール=アルベール・ローランスという画家とアルジェリアを旅し、そのアフリカの大地で人間の野生というものに触れた。これが一大転機となって『パリュード』を書いて、思いがけぬ成功をおさめた。これは、理知に疲れたパリの世紀末の空気、生命感をなくした大都会に対する倦怠と嫌悪を、皮肉と風刺をこめて書いたもので、ジッドを初めて“作家ジッド”とした著作だった。それは、ジッドの前を覆っていた黒い帳をパッと切り落とすものであったと同時に、それまでの象徴派詩人たちとの訣別でもあった。
『パリュード』につづいて矢継ぎ早やに作品が書かれ、『地の糧』もまた、神秘と野生に満ちたアフリカの大地への情熱的な讃歌、生命感の讃仰であり、これが彼の創作のエネルギー源となって、以降、『背徳者』『狭き門』『イザベル』『法王庁の抜け穴』『一粒の麦もし死なずば』『田園交響楽』など、よく知られる世界的な名作を次つぎに生み出していった。壮年期に至っては、社会的な問題、政治的な問題に対する発言も多くなり、旅行記『コンゴ紀行』では、ヨーロッパ列強の野心、資本主義的帝国主義の巨大な機構に鵜呑みにされ、無惨に踏みしだかれていくアフリカ植民地の姿をリアリスティックに描いて、その非道ぶりを正面から告発している。
サン=テグジュペリが『星の王子さま』を献じているレオン・ヴェルト(1878〜1955)は、反ファッシズム同盟の会長をつとめていたユダヤ人作家であり美術評論家でもあったが、植民地主義批判を中心とする反戦思想家。当時、大旋風を巻き起こした彼のスターリン批判は、じつはジッドの『ソビエト紀行』のスターリン独裁制批判の思想に依拠し、それを敷衍したもので、ジッドに多大な影響を受けていたことが知れる。
1944年7月31日、44歳という若さではるかな空の巡礼に旅だっていった“星の王子さま”に、74歳の大作家がどんな追悼の辞を述べたのか、わたしは知らない。これも歴史的な運命というべきか、その日からわずかのち、8月25日にはナチス・ドイツの占領下にあったパリは解放された。
若いときから貴族社会の保守反動思想を棄て、カトリックの信仰と王党主義に替わる新しい思想、新しい生き方を求めつづけた男。信念に忠実に生き、良心の命ずるところへ向けてまっすぐ行動した男。その存在はいまも異彩を放って人びとの胸のなかに輝きつづけている。

*「丘の上文庫だより」第45号別刷所収 口演記録より
Posted by 〔がの〕さん at 15:57│Comments(2)
│名作鑑賞〔海外〕
この記事へのコメント
はじめまして、ポコです。訪問ありがとうございます。
過去の記事でスサノオの命の記事、興味深く読ませていただきました。
この手の話は大好きです、過去にさかのぼって読ませていただいて
いいですか?そして星の王子様の話も好きです。
過去の記事でスサノオの命の記事、興味深く読ませていただきました。
この手の話は大好きです、過去にさかのぼって読ませていただいて
いいですか?そして星の王子様の話も好きです。
Posted by ポコ at 2014年08月16日 10:40
ポコさま。ありがとうございます。
あまり熱心とはいえぬブロガーで、勝手なことばかり書いてまいりました。
多くはほかの媒体に書いたり話したりしてきた記事を再整理したもので、
最近は読書会も読書指導もしておりませんで、いささか新鮮味に欠けることを感じています。
それでも、今更ながら、おかげさまにて世界のすぐれた文芸作品に出会ってきた幸運を思い、感謝しております。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。
ポコさまにおかれましても、その道でお元気にご精励くださいますよう…。
あまり熱心とはいえぬブロガーで、勝手なことばかり書いてまいりました。
多くはほかの媒体に書いたり話したりしてきた記事を再整理したもので、
最近は読書会も読書指導もしておりませんで、いささか新鮮味に欠けることを感じています。
それでも、今更ながら、おかげさまにて世界のすぐれた文芸作品に出会ってきた幸運を思い、感謝しております。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。
ポコさまにおかれましても、その道でお元気にご精励くださいますよう…。
Posted by 〔がの〕さん at 2014年08月17日 08:31
at 2014年08月17日 08:31
 at 2014年08月17日 08:31
at 2014年08月17日 08:31