2023年09月20日
P/ちいさいおうち V.L.バートン
ちいさいおうち
V.L.バートン

アメリカの人びとのこころの原郷とその生活史史
1942年、第二次世界大戦のさなかに生まれた作品。
19世紀、アメリカの開拓時代に建てられた小さなおうちが、静かな丘陵地にポツンと立っている。リンゴの木、ヒナギクなどの草花に囲まれて、おだやかに、幸せそうに。毎日はそれぞれ違う日とはいえ、小さなおうちだけは、いつもと同じ。
しかし、あるとき、機具を持った人たちがやってきてまわりの土地を測量していったあと、スチームシャベルなどの大型建設機械が入ってきて、ヒナギクの丘を切り崩し、たちまち大きな道路をつくっていった。やがてその道路をたくさんの車が行き来し、道の両側にガソリンスタンドが立ち、さまざまな商店や家が建ちならび、畑や林は消え、大きな家やアパート、公団住宅ができていった。静かな夜は奪われ、月も星も見えない。街灯がひと晩じゅう灯り、車の列は途切れることがない。
小さないおうちに住むひとはなく、だれからも見捨てられているが、持ち主がわからないのでお金で売り買いできないまま、じいっとそこを動かない。電車が走る、高架線が通る、人びとはせかせかと右へ左へ駆けまわる。空気はほこりと煙で汚れ、ごうごうというやかましい音に包まれ、小さいおうちはたえずガタガタと揺れる。さらには、小さなおうちのまわりにあった大きな家や公団住宅も取り壊され、今度は25階、35階の高層ビルがニョキニョキと建つ。もう、町は季節を失い、不眠の大都会へと変わってしまった。
小さいおうちは、むかしの静けさと幸せな日々を思い、自然にあふれたいなかのことを夢にみる。ペンキは剥げ、窓は破れてすっかりみすぼらしくなっていても、土台も壁も屋根も昔のまま、しっかりしていてびくともしない。ようやくこの家を建てた人の何代目かの子孫があらわれ、引っ越しを決める。ジャッキでまるごと車に乗せられた小さいおうちは、ずうっと離れた広い野原のまん中の小さな丘のうえに移された。ここには、朝がありひる昼があり夜があり四季があった。人が住むようになり、外壁は明るい色に塗りなおされる。小さいおうちは、もう二度と町には住みたくないと思った。
自然や簡素な生活から遠ざかれば遠ざかるほど、人は幸福から遠ざかることを言い、自然と人間の調和ある暮らしを求めるアメリカ精神の原型をあらわして、絵と文が間然することなく一致していることなどが高く評価され、1943年のコールデコット賞を受けた名作童話。
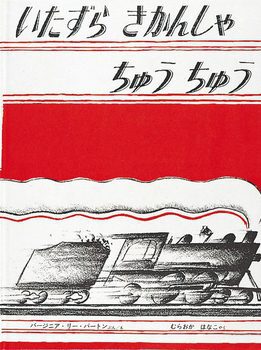
バージニア・リー・バートンVirginia Lee Burton米・1909-1968 石井桃子訳のこの「ちいさいおうち」をはじめ、「いたずらきかんしゃ ちゅうちゅう」「せいめいのれきし」「マイク・マリガンとスチームシォベル」「名馬キャリコ」「はたらきもののじょせつしゃ けいてぃー」などの名作絵本で、わが国でもおなじみですね。いずれも作者の現実的な生活実感のなかから生まれた絵本。
19世紀の初期に建てられたこのちいさいいえが、フォーリー・コーヴの大通りから約450メートル離れた、静かな丘の低い傾斜地に移されてきたのは1938年という。手入れが施され、ここに住むようになったのがバートン家の人たち。結婚後1年目からこの家に住み、ふたりの子どもを育て、たくさんの絵本作品をつくり、1968年に亡くなるまで、作者はここで暮らした。この丘のうえの家に移ってくるまでの1世紀にわたる星霜のなか、ちいさなおうちは画面のまん中に、ときには幸せそうに、ときには困惑して泣いているような表情を見せながら、もとのところにすわりつづける。しかし、さすがに時流の波には抵抗するすべもなく、それでも結局、幸いにも自然のリズムのある土地へと移される。
乗り物の変遷で時代の流れをあらわし、太陽の動きで一日の変化を、月の満ち欠けで一か月の変化を、四季の移ろいで一年の変化をとらえて、「時」の流れと歴史を表現するみごとな趣向にも注目したい。
V.L.バートン

アメリカの人びとのこころの原郷とその生活史史
1942年、第二次世界大戦のさなかに生まれた作品。
19世紀、アメリカの開拓時代に建てられた小さなおうちが、静かな丘陵地にポツンと立っている。リンゴの木、ヒナギクなどの草花に囲まれて、おだやかに、幸せそうに。毎日はそれぞれ違う日とはいえ、小さなおうちだけは、いつもと同じ。
しかし、あるとき、機具を持った人たちがやってきてまわりの土地を測量していったあと、スチームシャベルなどの大型建設機械が入ってきて、ヒナギクの丘を切り崩し、たちまち大きな道路をつくっていった。やがてその道路をたくさんの車が行き来し、道の両側にガソリンスタンドが立ち、さまざまな商店や家が建ちならび、畑や林は消え、大きな家やアパート、公団住宅ができていった。静かな夜は奪われ、月も星も見えない。街灯がひと晩じゅう灯り、車の列は途切れることがない。
小さないおうちに住むひとはなく、だれからも見捨てられているが、持ち主がわからないのでお金で売り買いできないまま、じいっとそこを動かない。電車が走る、高架線が通る、人びとはせかせかと右へ左へ駆けまわる。空気はほこりと煙で汚れ、ごうごうというやかましい音に包まれ、小さいおうちはたえずガタガタと揺れる。さらには、小さなおうちのまわりにあった大きな家や公団住宅も取り壊され、今度は25階、35階の高層ビルがニョキニョキと建つ。もう、町は季節を失い、不眠の大都会へと変わってしまった。
小さいおうちは、むかしの静けさと幸せな日々を思い、自然にあふれたいなかのことを夢にみる。ペンキは剥げ、窓は破れてすっかりみすぼらしくなっていても、土台も壁も屋根も昔のまま、しっかりしていてびくともしない。ようやくこの家を建てた人の何代目かの子孫があらわれ、引っ越しを決める。ジャッキでまるごと車に乗せられた小さいおうちは、ずうっと離れた広い野原のまん中の小さな丘のうえに移された。ここには、朝がありひる昼があり夜があり四季があった。人が住むようになり、外壁は明るい色に塗りなおされる。小さいおうちは、もう二度と町には住みたくないと思った。
自然や簡素な生活から遠ざかれば遠ざかるほど、人は幸福から遠ざかることを言い、自然と人間の調和ある暮らしを求めるアメリカ精神の原型をあらわして、絵と文が間然することなく一致していることなどが高く評価され、1943年のコールデコット賞を受けた名作童話。
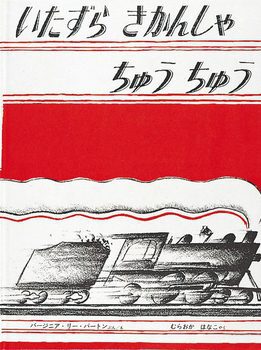
バージニア・リー・バートンVirginia Lee Burton米・1909-1968 石井桃子訳のこの「ちいさいおうち」をはじめ、「いたずらきかんしゃ ちゅうちゅう」「せいめいのれきし」「マイク・マリガンとスチームシォベル」「名馬キャリコ」「はたらきもののじょせつしゃ けいてぃー」などの名作絵本で、わが国でもおなじみですね。いずれも作者の現実的な生活実感のなかから生まれた絵本。
19世紀の初期に建てられたこのちいさいいえが、フォーリー・コーヴの大通りから約450メートル離れた、静かな丘の低い傾斜地に移されてきたのは1938年という。手入れが施され、ここに住むようになったのがバートン家の人たち。結婚後1年目からこの家に住み、ふたりの子どもを育て、たくさんの絵本作品をつくり、1968年に亡くなるまで、作者はここで暮らした。この丘のうえの家に移ってくるまでの1世紀にわたる星霜のなか、ちいさなおうちは画面のまん中に、ときには幸せそうに、ときには困惑して泣いているような表情を見せながら、もとのところにすわりつづける。しかし、さすがに時流の波には抵抗するすべもなく、それでも結局、幸いにも自然のリズムのある土地へと移される。
乗り物の変遷で時代の流れをあらわし、太陽の動きで一日の変化を、月の満ち欠けで一か月の変化を、四季の移ろいで一年の変化をとらえて、「時」の流れと歴史を表現するみごとな趣向にも注目したい。
2021年04月08日
C/バーバ・ヤガー③
バーバ・ヤガーとロシアの妖精たち③

お話ずきのロシア国民
こうした妖怪ばなしは、ロシアでは「ブィリーチカ」と呼ばれています。死んだ人や悪魔、レーシーを代表選手とする自然霊などにまつわるお話で、今も昔も、おとなにも子どもにも、たいへん人気があるんですね。
ブィリーチカといえば、ツルゲーネフ(1818~83)を忘れることはできません。日本でよく読まれている『猟人日記』という作品のなかに「ベージンの草野」という美しい短篇があります。知っているかな、きみは?
えぞやまどりの猟をしていた主人公は、知らない間に林のなかで道に迷い、夕闇がせまるころ、「ベージンの草野」と呼ばれる、とほうもなく広い草野に来てしまいます。ふと、焚火を見つけます。そのまわりには5人の少年たち。近くの村のお百姓の子どもたちで、馬の野飼いに来ていたのです。夏の昼どきはハエやアブがうるさくて、馬たちはゆっくり休めない、そこで馬の群れを夕方から夜明けまで野飼いにする習慣があったようです。その仕事をするのが、ふつう、子どもでした。
7歳から14歳くらいまでの少年たちは、焚火を囲み、じゃがいもの煮えるのを待ちながら、それぞれが見聞きしたことを次つぎに語りあいます。ロシアの民話はこんなところで、こんな形で生まれ育ったんだな、ということがよくわかりますね。ほんとに彼らはお話が好きなんです。

イワン・ビリービンによるムソルグスキー「展覧会の絵」のバーバ・ヤガー
ひとりの子は、紙すき場で聞いたという家魔「ダマヴォイ」のことを話します。その姿を見たわけではないんだけど、水車のまわりを歩いているらしく、床板がみしみし音をたててしなったり、だれも水門をさわらないのに、急に水が水車に流れこんだり、また自然に止まったりするという不思議な体験。
別の子は、お父さんから聞いたという水の精「ルサルカ」の話をします。月の光を浴びながら、木の枝にすわってゆらゆら揺れ、息が止まりそうなほど笑いころげています。「身体じゅうが透き通るように白くって、枝に腰かけているところは、まるで鯉かカワギスか…、でなけりゃ、ほら、フナかなんぞのように、白っぽく銀色に光ってるんだ」「…それでやっと十字を切るとな、ルサルカは笑うのをやめてしまって、急においおい泣きじゃくるじゃないか…、泣きながら髪の毛で目を拭くんだけど、その髪の毛というのが、まるで大麻のようにまっ青のなのさ」(米川正夫訳)と描かれています。目も緑、声はとても細く悲しそうで、まるでガマの声みたいだったともいいます。

水の精・ルサルカ 水に身を沈めて果てた少女の霊とも言われる(木彫り)
このルサルカ、よく水に引き込んでひとを殺します。そしておもしろいのは、ひとをくすぐって笑い殺してしまうのが十八番(おはこ)だということ。森林地帯の奥地の湖水にすむ妖怪ですね。
さらには、「トリーシカ」の話。これはまた、ものすごい顔をした、悪知恵のはたらくやつで、いずれいつかこの世界にやってくるといわれる化け物。つかまえるなんてできやしない。鎖でしばりつけても、そいつがポンと手をうつとパラリとほどけちゃう。水を飲むひしゃくのなかにもぐりこんですがたを隠すなんてことも、へっちゃらでやるようなやつなんだね。
ほかにも、少年たちの夜語りには、森の主、河の主などなどが登場し、夜明け近くまでつづきます。ロシアの人びとの生活のあらゆるところでこうした民話が息づいているんですね。途方もなく広い自然のたたずまい、そのきびしさもあって、すばらしい想像力、空想力を備えているんだね、ロシアの人びとは。(了)
※菅野耿・再話『森の魔女 バーバ・ヤガー』(当サイト①2019.7.22、②同8.29所収)を参照ください。

お話ずきのロシア国民
こうした妖怪ばなしは、ロシアでは「ブィリーチカ」と呼ばれています。死んだ人や悪魔、レーシーを代表選手とする自然霊などにまつわるお話で、今も昔も、おとなにも子どもにも、たいへん人気があるんですね。
ブィリーチカといえば、ツルゲーネフ(1818~83)を忘れることはできません。日本でよく読まれている『猟人日記』という作品のなかに「ベージンの草野」という美しい短篇があります。知っているかな、きみは?
えぞやまどりの猟をしていた主人公は、知らない間に林のなかで道に迷い、夕闇がせまるころ、「ベージンの草野」と呼ばれる、とほうもなく広い草野に来てしまいます。ふと、焚火を見つけます。そのまわりには5人の少年たち。近くの村のお百姓の子どもたちで、馬の野飼いに来ていたのです。夏の昼どきはハエやアブがうるさくて、馬たちはゆっくり休めない、そこで馬の群れを夕方から夜明けまで野飼いにする習慣があったようです。その仕事をするのが、ふつう、子どもでした。
7歳から14歳くらいまでの少年たちは、焚火を囲み、じゃがいもの煮えるのを待ちながら、それぞれが見聞きしたことを次つぎに語りあいます。ロシアの民話はこんなところで、こんな形で生まれ育ったんだな、ということがよくわかりますね。ほんとに彼らはお話が好きなんです。

イワン・ビリービンによるムソルグスキー「展覧会の絵」のバーバ・ヤガー
ひとりの子は、紙すき場で聞いたという家魔「ダマヴォイ」のことを話します。その姿を見たわけではないんだけど、水車のまわりを歩いているらしく、床板がみしみし音をたててしなったり、だれも水門をさわらないのに、急に水が水車に流れこんだり、また自然に止まったりするという不思議な体験。
別の子は、お父さんから聞いたという水の精「ルサルカ」の話をします。月の光を浴びながら、木の枝にすわってゆらゆら揺れ、息が止まりそうなほど笑いころげています。「身体じゅうが透き通るように白くって、枝に腰かけているところは、まるで鯉かカワギスか…、でなけりゃ、ほら、フナかなんぞのように、白っぽく銀色に光ってるんだ」「…それでやっと十字を切るとな、ルサルカは笑うのをやめてしまって、急においおい泣きじゃくるじゃないか…、泣きながら髪の毛で目を拭くんだけど、その髪の毛というのが、まるで大麻のようにまっ青のなのさ」(米川正夫訳)と描かれています。目も緑、声はとても細く悲しそうで、まるでガマの声みたいだったともいいます。

水の精・ルサルカ 水に身を沈めて果てた少女の霊とも言われる(木彫り)
このルサルカ、よく水に引き込んでひとを殺します。そしておもしろいのは、ひとをくすぐって笑い殺してしまうのが十八番(おはこ)だということ。森林地帯の奥地の湖水にすむ妖怪ですね。
さらには、「トリーシカ」の話。これはまた、ものすごい顔をした、悪知恵のはたらくやつで、いずれいつかこの世界にやってくるといわれる化け物。つかまえるなんてできやしない。鎖でしばりつけても、そいつがポンと手をうつとパラリとほどけちゃう。水を飲むひしゃくのなかにもぐりこんですがたを隠すなんてことも、へっちゃらでやるようなやつなんだね。
ほかにも、少年たちの夜語りには、森の主、河の主などなどが登場し、夜明け近くまでつづきます。ロシアの人びとの生活のあらゆるところでこうした民話が息づいているんですね。途方もなく広い自然のたたずまい、そのきびしさもあって、すばらしい想像力、空想力を備えているんだね、ロシアの人びとは。(了)
※菅野耿・再話『森の魔女 バーバ・ヤガー』(当サイト①2019.7.22、②同8.29所収)を参照ください。
2021年03月11日
C/バーバ・ヤガー②
バーバ・ヤガーとロシアの妖精たち②

民話はロシアの宝もの
森の支配者といえば、ロシアのなかでいちばんのおなじみは、レーシー。この森の精霊は、森を通るひとを脅して追い出すか、道を迷わせて、とんでもないところへ連れ込んでしまう。ひとをさらうこともある。これはロシアの北にも南にもたいへん広く分布していて、バーバ・ヤガーはこのレーシーから変化して生まれたと考えるひとも少なくありません。
実際、ロシアの北のほうは、まさに森の国です。針葉樹が暗く単調にどこまでもつづき、うっかり迷い込んだら方角もわからず、出られなくなってしまうこともあるといわれます。湿地には底なし沼も多い。熊お狼などの獣たちの目がものかげから光っています。盗賊たち、あるいは脱走兵の秘密の隠れ家もあります。こんなおそろしい自然ですから、人びとはこころをふるわせながらいろいろと想像をめぐらせます。
そうです、妖怪やふしぎな化け物たちは人間の想像力が生みだしたものです。それそれの国の自然風土と深い関係をもちながら、世界のどの国、どの民族にも独自の妖精たちがいます。日本でいったら、きみ、どんなんのを知ってる? ほら、アマンジャクがそうだろう。山姥(やまんば)や天狗、座敷童子、枕返し…なんてのもいるし、海坊主、小豆洗い婆などもその仲間だね。

ロシアには、森のなかに、さきほどのレーシーや山親爺ゴールヌイがいるし、水のなかにはルサルカやヴォジャノイ、穀物の乾燥小屋にはオビンニク、そして家のなか、とくにペチカのうしろや煙突のわきにはダマヴォイという妖精がよくいます。ほかにももっともっといて、それぞれ名前をもっています。北欧で妖精のことを「トロル」とひとつに呼んでしまうのとはずいぶん違いますね。
こうしたものに想像力を刺激されて、ロシアには世界のどの国よりもたくさんの民話が生まれました。この民話こそロシア最大の宝ものだと言ったひともいます。
トルストイが民話から『イワンのばか』ほか、たくさんのすばらしい物語をつくっていることは、もうよく知っているよね。プーシキンも『サルタン王の話』など、珠玉の民話詩を書いています。ほかにも、その民話や伝説から名作を書いている大文豪がいっぱいいますよ。
たとえば、ゴーゴリ(1809~1852)。『外套』という名作を書き、近代ロシア文学の父といわれるこの文豪の『ディカーニカ近郷夜話』には、ウクライナ地方を舞台にして活躍する妖精や悪魔が生き生きと書かれています。このなかの『イワン・クパーラの前夜』には、もうおなじみのバーバ・ヤガーとその奇妙な小屋の話もちゃんと出てきます。この作家は“ヴィー”という、これもまたへんてこな妖怪、地中に住むおっそろしい老人のことなども書いています。チェーホフという作家も知っているでしょ。有名な『ワーニャ伯父さん』、あの作品のもとになっているのが『森の精レーシー』。ね、ロシアの森は創造力の源泉でもあったんだね。おもしろいから、きみもぜひ読んでごらんよ。(以下、つづく)
※菅野耿・再話『森の魔女 バーバ・ヤガー』(①2019.7.22、②同8.29所収)を参照ください。

民話はロシアの宝もの
森の支配者といえば、ロシアのなかでいちばんのおなじみは、レーシー。この森の精霊は、森を通るひとを脅して追い出すか、道を迷わせて、とんでもないところへ連れ込んでしまう。ひとをさらうこともある。これはロシアの北にも南にもたいへん広く分布していて、バーバ・ヤガーはこのレーシーから変化して生まれたと考えるひとも少なくありません。
実際、ロシアの北のほうは、まさに森の国です。針葉樹が暗く単調にどこまでもつづき、うっかり迷い込んだら方角もわからず、出られなくなってしまうこともあるといわれます。湿地には底なし沼も多い。熊お狼などの獣たちの目がものかげから光っています。盗賊たち、あるいは脱走兵の秘密の隠れ家もあります。こんなおそろしい自然ですから、人びとはこころをふるわせながらいろいろと想像をめぐらせます。
そうです、妖怪やふしぎな化け物たちは人間の想像力が生みだしたものです。それそれの国の自然風土と深い関係をもちながら、世界のどの国、どの民族にも独自の妖精たちがいます。日本でいったら、きみ、どんなんのを知ってる? ほら、アマンジャクがそうだろう。山姥(やまんば)や天狗、座敷童子、枕返し…なんてのもいるし、海坊主、小豆洗い婆などもその仲間だね。

ロシアには、森のなかに、さきほどのレーシーや山親爺ゴールヌイがいるし、水のなかにはルサルカやヴォジャノイ、穀物の乾燥小屋にはオビンニク、そして家のなか、とくにペチカのうしろや煙突のわきにはダマヴォイという妖精がよくいます。ほかにももっともっといて、それぞれ名前をもっています。北欧で妖精のことを「トロル」とひとつに呼んでしまうのとはずいぶん違いますね。
こうしたものに想像力を刺激されて、ロシアには世界のどの国よりもたくさんの民話が生まれました。この民話こそロシア最大の宝ものだと言ったひともいます。
トルストイが民話から『イワンのばか』ほか、たくさんのすばらしい物語をつくっていることは、もうよく知っているよね。プーシキンも『サルタン王の話』など、珠玉の民話詩を書いています。ほかにも、その民話や伝説から名作を書いている大文豪がいっぱいいますよ。
たとえば、ゴーゴリ(1809~1852)。『外套』という名作を書き、近代ロシア文学の父といわれるこの文豪の『ディカーニカ近郷夜話』には、ウクライナ地方を舞台にして活躍する妖精や悪魔が生き生きと書かれています。このなかの『イワン・クパーラの前夜』には、もうおなじみのバーバ・ヤガーとその奇妙な小屋の話もちゃんと出てきます。この作家は“ヴィー”という、これもまたへんてこな妖怪、地中に住むおっそろしい老人のことなども書いています。チェーホフという作家も知っているでしょ。有名な『ワーニャ伯父さん』、あの作品のもとになっているのが『森の精レーシー』。ね、ロシアの森は創造力の源泉でもあったんだね。おもしろいから、きみもぜひ読んでごらんよ。(以下、つづく)
※菅野耿・再話『森の魔女 バーバ・ヤガー』(①2019.7.22、②同8.29所収)を参照ください。





