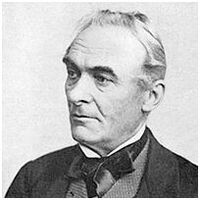2024年11月16日
F/S.モームの憂鬱
サマーセット・モームを追って

◆S.モームの憂鬱
William Somerset Maugham 1874年、4人兄弟の末っ子としてパリのシャンゼリゼ近くで生まれる(~1965)。アイルランド系の血筋を引き、父はイギリス大使館の顧問弁護士、母は王統の血を引く美女だったが、モーム8歳のとき結核で死去。父も10歳のとき癌で死亡。イギリス・ケント州で牧師をしていた叔父のもとに引き取られる。
日本の作家、樋口一葉(1872~96)、島崎藤村(1872~1943)、泉鏡花(1873~1939)、柳田国男(1853~1962)、与謝野晶子(1878~1942)らとほぼ同時代人。
どもりで背が低いことをコンプレックスにし、女ぎらいになったという。このことの反映か、作品は懐疑的で、人間の不可解性、謎の多い人間の魂を抉りとり、人間を矛盾の塊として描きつづけることになる、…物質主義者であったり無神論者であったり、拝金主義者であったり、女ぎらいであったりする人物像……。「金というものは第六感みたいなもので、これなくしては他の五感も完全な働きはできぬ」、金なしでは恋愛さえもできない、といった冷嘲的な諷刺劇ふうの戯曲を初期のころはさかんに書いた。
◆宇宙の果てまで彷徨う男の魂
40歳のとき、第一次世界大戦の従軍、スイス・ジュネーブでスパイ活動。時間的な余裕があり、執筆活動をはじめて『人間の絆』を書きあげ出版したが、評判にはならず。のちに健康を害して渡米、ハワイ、サモア、タヒチなどの南海諸島にあそんだ。このときポール・ゴーギャンの生き方を知り調査、セザンヌ、ランボー、ゴッホら、時の芸術家の生き方とからめて『月と六ペンス』の想を練る。「男の魂は宇宙のさいはてまでもさまよって飽きることを知らないが、女はそいつを家計簿の枠の中に閉じ込めてしまおうとする」といった見方も。
この作品では、チャールズ・ストリックランドという四十男、ロンドンの株式取引所員のすがたが描かれる。仕事に失望して突然家出し、絵を描きたいとパリへ。そして47歳でタヒチ島にわたり、土地の娘アタと原始林のなかで生活、風土病のらい病にかかって死ぬが、死ぬ前に、盲目になって家の壁面じゅうに「天地創造」を描き、死んだらそれをすっかり焼却させる。
アタは、男の邪魔をせず、ひたすら男に尽くす奉仕型の女性、ほかに馴染んだ女性に、恋愛希求型のブランチ・ストループ、見栄っ張りで社交型、ボヘミアンタイプのエイミーがいた。女ぎらいの作者の心底には、無垢なまでに自分に尽くすアタ以外は、古靴のように捨てるほかなかった。「月」とは何か? 人間を狂気にする芸術的蠱惑・魔術的情熱であり、「六ペンス」とは、古草履のように主人公が否定し棄てた世俗的な因襲と絆のことであったろうか。

◆皮肉と諧謔に満ちた喜劇的な世界
ゴ―ギャンをモデルにしたこの『月と六ペンス』を出版すると、いきなりベストセラーに。その文章の特徴は単純で平明、しかしそこに微妙な陰影をもっているというスタイル。この作品の発刊を機に『人間の絆』も見直され、1910年代の世界の流行作家の一人となる。これは半自伝的な作品で、当初はほとんど評判にならなかったが、「これを書くことにより、自分の中のものが浄化され、本格的な作家への道に立つことができた」。以後、数々の旅行記や小品短篇集、長編の『お菓子とビール』『クリスマス休暇』『剃刀の刃』、自伝的評論『要約The Summing Up』、そして最後の長編『カタリーナ』などを書き残した。
S.モームの人生哲学(『人間の絆』より)
「人生も無意味なものなれば、人間の生もまた虚しい営みに過ぎぬ。生まれようと、生まれまいと、生きようと、死のうと、それは何のことでもない。生の無意味、死もまた無意味……あたかも絨毯の織匠が、ただその審美感の喜びを満足させるためだけにその模様を織りだしたように、人もまたそのように人生を生きればよい。畢竟、人生は一つの模様意匠にすぎないと、そう考えてよいのだ。特にあることをしなければならないという意味もなければ、必要もない。ただすべては彼自身の喜びのためにするのだ。……フィリップは幸福への願望を棄てることによって、彼の最後の迷妄を振り落とした」。後年に書かれた評論“The Summing Up”にも、これと同様の、冷淡に突き放したような記述が見られる。
作家生活にピリオドを打ったあとの最晩年には、極東方面を旅行、東京や京都に4週間ほど滞在したこともあるが、91歳、南仏ニースのアングロ・アメリカン病院にて死亡。

◆S.モームの憂鬱
William Somerset Maugham 1874年、4人兄弟の末っ子としてパリのシャンゼリゼ近くで生まれる(~1965)。アイルランド系の血筋を引き、父はイギリス大使館の顧問弁護士、母は王統の血を引く美女だったが、モーム8歳のとき結核で死去。父も10歳のとき癌で死亡。イギリス・ケント州で牧師をしていた叔父のもとに引き取られる。
日本の作家、樋口一葉(1872~96)、島崎藤村(1872~1943)、泉鏡花(1873~1939)、柳田国男(1853~1962)、与謝野晶子(1878~1942)らとほぼ同時代人。
どもりで背が低いことをコンプレックスにし、女ぎらいになったという。このことの反映か、作品は懐疑的で、人間の不可解性、謎の多い人間の魂を抉りとり、人間を矛盾の塊として描きつづけることになる、…物質主義者であったり無神論者であったり、拝金主義者であったり、女ぎらいであったりする人物像……。「金というものは第六感みたいなもので、これなくしては他の五感も完全な働きはできぬ」、金なしでは恋愛さえもできない、といった冷嘲的な諷刺劇ふうの戯曲を初期のころはさかんに書いた。
◆宇宙の果てまで彷徨う男の魂
40歳のとき、第一次世界大戦の従軍、スイス・ジュネーブでスパイ活動。時間的な余裕があり、執筆活動をはじめて『人間の絆』を書きあげ出版したが、評判にはならず。のちに健康を害して渡米、ハワイ、サモア、タヒチなどの南海諸島にあそんだ。このときポール・ゴーギャンの生き方を知り調査、セザンヌ、ランボー、ゴッホら、時の芸術家の生き方とからめて『月と六ペンス』の想を練る。「男の魂は宇宙のさいはてまでもさまよって飽きることを知らないが、女はそいつを家計簿の枠の中に閉じ込めてしまおうとする」といった見方も。
この作品では、チャールズ・ストリックランドという四十男、ロンドンの株式取引所員のすがたが描かれる。仕事に失望して突然家出し、絵を描きたいとパリへ。そして47歳でタヒチ島にわたり、土地の娘アタと原始林のなかで生活、風土病のらい病にかかって死ぬが、死ぬ前に、盲目になって家の壁面じゅうに「天地創造」を描き、死んだらそれをすっかり焼却させる。
アタは、男の邪魔をせず、ひたすら男に尽くす奉仕型の女性、ほかに馴染んだ女性に、恋愛希求型のブランチ・ストループ、見栄っ張りで社交型、ボヘミアンタイプのエイミーがいた。女ぎらいの作者の心底には、無垢なまでに自分に尽くすアタ以外は、古靴のように捨てるほかなかった。「月」とは何か? 人間を狂気にする芸術的蠱惑・魔術的情熱であり、「六ペンス」とは、古草履のように主人公が否定し棄てた世俗的な因襲と絆のことであったろうか。

◆皮肉と諧謔に満ちた喜劇的な世界
ゴ―ギャンをモデルにしたこの『月と六ペンス』を出版すると、いきなりベストセラーに。その文章の特徴は単純で平明、しかしそこに微妙な陰影をもっているというスタイル。この作品の発刊を機に『人間の絆』も見直され、1910年代の世界の流行作家の一人となる。これは半自伝的な作品で、当初はほとんど評判にならなかったが、「これを書くことにより、自分の中のものが浄化され、本格的な作家への道に立つことができた」。以後、数々の旅行記や小品短篇集、長編の『お菓子とビール』『クリスマス休暇』『剃刀の刃』、自伝的評論『要約The Summing Up』、そして最後の長編『カタリーナ』などを書き残した。
S.モームの人生哲学(『人間の絆』より)
「人生も無意味なものなれば、人間の生もまた虚しい営みに過ぎぬ。生まれようと、生まれまいと、生きようと、死のうと、それは何のことでもない。生の無意味、死もまた無意味……あたかも絨毯の織匠が、ただその審美感の喜びを満足させるためだけにその模様を織りだしたように、人もまたそのように人生を生きればよい。畢竟、人生は一つの模様意匠にすぎないと、そう考えてよいのだ。特にあることをしなければならないという意味もなければ、必要もない。ただすべては彼自身の喜びのためにするのだ。……フィリップは幸福への願望を棄てることによって、彼の最後の迷妄を振り落とした」。後年に書かれた評論“The Summing Up”にも、これと同様の、冷淡に突き放したような記述が見られる。
作家生活にピリオドを打ったあとの最晩年には、極東方面を旅行、東京や京都に4週間ほど滞在したこともあるが、91歳、南仏ニースのアングロ・アメリカン病院にて死亡。
F/スタインベック「二十日ネズミと人間」
F/「カルメン」メリメ
F/貧しき人びと ドストエフスキー
F/静かなるドン ショーロホフ
F/「カモメのジョナサン」R.バック
F/「赤い小馬」スタインベック
F/「カルメン」メリメ
F/貧しき人びと ドストエフスキー
F/静かなるドン ショーロホフ
F/「カモメのジョナサン」R.バック
F/「赤い小馬」スタインベック
Posted by 〔がの〕さん at 00:24│Comments(0)
│名作鑑賞〔海外〕