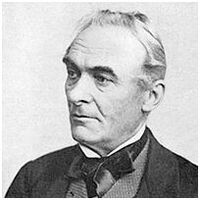2016年02月09日
F/ウェブスター「あしながおじさん」
ウェブスター「あしながおじさん」
想像力、コミュニケーションの根底にあるもの
「ねえ、おじさま、わたしは人間にとっていちばん必要なことは、想像力を持つことだと思います。想像力があれば、わたしたちは他人の立場になって考えることができます。そうすれば自然、親切になり、思いやりもでき、よくわかってあげられるようにもなります。その想像力は、子どものころに育てておくべきものです」――ウェブスター『あしながおじさん』(恩地三保子・訳)

阪神淡路大震災1995、新潟中越沖地震2007、東日本大震災2011、そして昨年9月の豪雨、鬼怒川決壊により常総市を襲った甚大な水の被害など、だれの記憶にもまだ新しい大災害。ここ1週間に限っても、桜島や霧島の火山噴火があり、ここ横浜にいてさえドキリと肝を冷やした3回にわたる震度3以上の荒っぽい揺れがありました。日本列島だけでなく、台湾南部では大地震でビルが倒壊して多くの犠牲者をだすなど、地球は怒っており、一寸先は闇、を思わせますね。しかも、日本列島に上陸する最近の台風はこれまでになく大型で、われわれの想像を越えて甚大な被害を容赦なくもたらすものになってしまいました。

そんななか、軽率なわたしは、さもわかったようなふうをして良寛さんのことば「死ぬ時節には死ぬがよく候」を引き、いい気になっていたような始末。とりわけ、新潟・中越大地震は、良寛さんがこれを書いた文政11(1828)年の大地震によく似ているんですね。いまの三条市を中心におきたマグニチュード7.4という地震。死者1,607人(一説には1万人)、倒壊家屋1万3千余戸という、今回のものよりもだいぶ大きい地震でした。文人なかまの山田杜皐(とこう)に宛てた災害見舞い文の一部で、そんなときには仕方ないじゃないか、死ぬときが来たら人間は死ぬのよ、もう十分に生きたじゃないか、と親しい間がらだからいえることば。ここに良寛さんの、自然を受け容れ、自然と融和しつつ生きる潔さを見、人間のもつ弱さに徹した無抵抗主義と、自然と魂を全一にする姿を見て、これだ! と感動していたわけです。
ですが、最近のひどい被災の現実を目の前にするとき、ただ呆然とし、おのれの想像力の欠如を知ってたじろぎ、ごめんなさいと愧じてお詫びするしかないこのごろ。
神の怒りにさらされた日本列島。地球というこの星で、この地上で、自分がひとりだけ生き残ったとしたらどうだろう、親もいない、兄弟姉妹もいない、愛する人も友人も、隣人もいない、自分のほかに声をかける存在がどこにもない……、そんな孤絶した世界の寂しさを想像してみる。あるいはその逆を。おびただしい群集がひしめきあうなかにあって、だれ一人として知った顔がない、親しみある顔がない、老いて自由に、機敏には動けぬ身、周囲すべてが自分の存在など歯牙にもかけずさっさと通りすぎていく、場合によっては、その一人ずつが恐ろしい敵意の一瞥を投げてすれちがっていく…。
あまりにもつらい想像です。しかし、これは現実ばなれをした極端すぎる想像でしょうか。想像してはいけないことでしょうか。

『あしながおじさん』では、孤児院出身のジュディーは、そのゆたかな想像力とアメリカ的なパイオニア・スピリット、独立心で、作家への道とともに児童福祉を中心とする社会事業へ身を投じていくわけだが、その一方、ラ・ロシュフーコーが皮肉にこんな真実を語ってもいる。
「われわれは皆、他人の不幸には充分耐えられるだけの強さを持っている」
そうなんですね、このたびの災害を免れたものには、所詮、被災者たちのほんとうの困難さと苦しみは理解できない。気の毒とは思っても、せいぜい無理のない程度の寄付をする程度、泣くに泣けないその死ぬような苦しみとは別に、日常の小さな幸せのなかに埋没してすぐに忘れていくのが凡夫の習わし。
名門女子大で、良家の子女に囲まれてすごすジュディー。〝あしながおじさん〟の援助で何不自由ないとはいえ、孤児院出身であるというコンプレックスをかかえ、親友にさえそれを語れない。そんなジュディーを支えているのは、どんな困難も明るく受けとめて、決して弱気を吐かない性格と、はてしないあこがれへむけて羽ばたく力強い“想像力”であったでしょう。
☆
「ジコチュー」ということばはもう古いようで、このごろあまり聞かなくなりました。しかしこの問題が解消されたわけではなく、いよいよ一般的、普遍的な社会現象になったため問題にされなくなったというにすぎない。他人が見えない、他者の痛みがわからないのは、事実、子どもの世界のことではなく、いま町を吹く風にはどこにいてもその冷たさが身に沁みる。それは、想像力、…コミュニケーションの根底にあるべき想像力が欠けているからといってよいような気がします。
いま、町に出て、レストランへ行ってもコンビニに行っても、本屋へいってもデパートへ行っても、たしかに若い人たちの元気な挨拶にぶつかります。溌剌と「いらっしゃいませ」「こんにちは」「またお来しくださいませ」……しかしそこには「まことのことばはうしなはれ」(宮沢賢治「春と修羅」)、マニュアル言語しかなく、場合によっては背中をむけていたりして、だれに向かって云っているのかわからず、うるさいだけでこちらには何も伝わってこない。ああ、こんなに人間が人間に関心を持たなくなってきたのか、このあとどうなるのだろうかと、あの声を聞くたびにさびしく思うときがあります。だからといって、わたし自身もご同様なのかも知れず、ぶつぶつ文句をいう筋合いではありませんが。
そんなことはありませんか。いまわたしたちに何がなくなったのか。…想像力です。
想像力、コミュニケーションの根底にあるもの
「ねえ、おじさま、わたしは人間にとっていちばん必要なことは、想像力を持つことだと思います。想像力があれば、わたしたちは他人の立場になって考えることができます。そうすれば自然、親切になり、思いやりもでき、よくわかってあげられるようにもなります。その想像力は、子どものころに育てておくべきものです」――ウェブスター『あしながおじさん』(恩地三保子・訳)

阪神淡路大震災1995、新潟中越沖地震2007、東日本大震災2011、そして昨年9月の豪雨、鬼怒川決壊により常総市を襲った甚大な水の被害など、だれの記憶にもまだ新しい大災害。ここ1週間に限っても、桜島や霧島の火山噴火があり、ここ横浜にいてさえドキリと肝を冷やした3回にわたる震度3以上の荒っぽい揺れがありました。日本列島だけでなく、台湾南部では大地震でビルが倒壊して多くの犠牲者をだすなど、地球は怒っており、一寸先は闇、を思わせますね。しかも、日本列島に上陸する最近の台風はこれまでになく大型で、われわれの想像を越えて甚大な被害を容赦なくもたらすものになってしまいました。

そんななか、軽率なわたしは、さもわかったようなふうをして良寛さんのことば「死ぬ時節には死ぬがよく候」を引き、いい気になっていたような始末。とりわけ、新潟・中越大地震は、良寛さんがこれを書いた文政11(1828)年の大地震によく似ているんですね。いまの三条市を中心におきたマグニチュード7.4という地震。死者1,607人(一説には1万人)、倒壊家屋1万3千余戸という、今回のものよりもだいぶ大きい地震でした。文人なかまの山田杜皐(とこう)に宛てた災害見舞い文の一部で、そんなときには仕方ないじゃないか、死ぬときが来たら人間は死ぬのよ、もう十分に生きたじゃないか、と親しい間がらだからいえることば。ここに良寛さんの、自然を受け容れ、自然と融和しつつ生きる潔さを見、人間のもつ弱さに徹した無抵抗主義と、自然と魂を全一にする姿を見て、これだ! と感動していたわけです。
ですが、最近のひどい被災の現実を目の前にするとき、ただ呆然とし、おのれの想像力の欠如を知ってたじろぎ、ごめんなさいと愧じてお詫びするしかないこのごろ。
神の怒りにさらされた日本列島。地球というこの星で、この地上で、自分がひとりだけ生き残ったとしたらどうだろう、親もいない、兄弟姉妹もいない、愛する人も友人も、隣人もいない、自分のほかに声をかける存在がどこにもない……、そんな孤絶した世界の寂しさを想像してみる。あるいはその逆を。おびただしい群集がひしめきあうなかにあって、だれ一人として知った顔がない、親しみある顔がない、老いて自由に、機敏には動けぬ身、周囲すべてが自分の存在など歯牙にもかけずさっさと通りすぎていく、場合によっては、その一人ずつが恐ろしい敵意の一瞥を投げてすれちがっていく…。
あまりにもつらい想像です。しかし、これは現実ばなれをした極端すぎる想像でしょうか。想像してはいけないことでしょうか。

『あしながおじさん』では、孤児院出身のジュディーは、そのゆたかな想像力とアメリカ的なパイオニア・スピリット、独立心で、作家への道とともに児童福祉を中心とする社会事業へ身を投じていくわけだが、その一方、ラ・ロシュフーコーが皮肉にこんな真実を語ってもいる。
「われわれは皆、他人の不幸には充分耐えられるだけの強さを持っている」
そうなんですね、このたびの災害を免れたものには、所詮、被災者たちのほんとうの困難さと苦しみは理解できない。気の毒とは思っても、せいぜい無理のない程度の寄付をする程度、泣くに泣けないその死ぬような苦しみとは別に、日常の小さな幸せのなかに埋没してすぐに忘れていくのが凡夫の習わし。
名門女子大で、良家の子女に囲まれてすごすジュディー。〝あしながおじさん〟の援助で何不自由ないとはいえ、孤児院出身であるというコンプレックスをかかえ、親友にさえそれを語れない。そんなジュディーを支えているのは、どんな困難も明るく受けとめて、決して弱気を吐かない性格と、はてしないあこがれへむけて羽ばたく力強い“想像力”であったでしょう。
☆
「ジコチュー」ということばはもう古いようで、このごろあまり聞かなくなりました。しかしこの問題が解消されたわけではなく、いよいよ一般的、普遍的な社会現象になったため問題にされなくなったというにすぎない。他人が見えない、他者の痛みがわからないのは、事実、子どもの世界のことではなく、いま町を吹く風にはどこにいてもその冷たさが身に沁みる。それは、想像力、…コミュニケーションの根底にあるべき想像力が欠けているからといってよいような気がします。
いま、町に出て、レストランへ行ってもコンビニに行っても、本屋へいってもデパートへ行っても、たしかに若い人たちの元気な挨拶にぶつかります。溌剌と「いらっしゃいませ」「こんにちは」「またお来しくださいませ」……しかしそこには「まことのことばはうしなはれ」(宮沢賢治「春と修羅」)、マニュアル言語しかなく、場合によっては背中をむけていたりして、だれに向かって云っているのかわからず、うるさいだけでこちらには何も伝わってこない。ああ、こんなに人間が人間に関心を持たなくなってきたのか、このあとどうなるのだろうかと、あの声を聞くたびにさびしく思うときがあります。だからといって、わたし自身もご同様なのかも知れず、ぶつぶつ文句をいう筋合いではありませんが。
そんなことはありませんか。いまわたしたちに何がなくなったのか。…想像力です。
Posted by 〔がの〕さん at 13:03│Comments(0)
│名作鑑賞〔海外〕