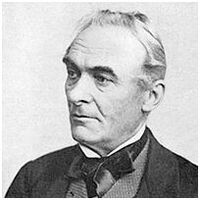2011年11月17日
F/バルザック「谷間の百合」
バルザック「谷間の百合」
こころの闇に咲く清純な大輪の花、崇高な愛のすがた
「谷間の百合」やっと読み終えました。「ゴリオ爺さん」のパリの社交界とは正反対の息苦しいほどの清い愛。モルソフ夫人の心の葛藤。そして愛に死ぬ衝撃。パリの社交界での成功のレールを引く夫人。そこに世俗的な愛が忍び寄ることを恐れながらも愛するフェリックスをパリに送り出す気持ちを思うと、それほどまでに深い愛だったのだと最後に気付きます。読みにくいと思いながらも惹かれるバルザックの作品です。〔Pwm さん〕
----------------------------
すごい! さすが、ですね。バルザックの名を知らない人はなくても、いまどきこの大河小説をひもとこうなんて人は、めったにいません。読書をよくするとされるみなさんのなかでも、最近『谷間の百合』や『ゴリオ爺さん』『従妹ベット』といったあたりを読んだという人は、たぶんいないはず。薄っぺらなもののうえで幼児顔して滑っているだけでなく、こういうものをじっくり読んでいただきたいですがね。だって、こういうものを読んだあとには、自分が新しくなったような、自分がひとつ確かに高められたような、そんな悦びがありますよね。新書などで表面的なその場限りの簡易知識をいくら詰め込んでもぜったいに得ることのできない、感動の深さがここにはあります。うわっ面の知識を追うことのむなしさを知るときでもあります。

『谷間の百合』――。もうずいぶん前に読んだもので、忘れてしまったことばかりですが、そうそう、バルザック自身を想わせる主人公のフェリックス。百合の花に譬えられる美しい貴婦人モルソフ夫人(アンリエット)。ふたりはある舞踏会で偶然に出会い、青年は踊ったあと思わず夫人の匂やかな肩に顔をうずめてキスをしてしまいます。愛情薄い家庭で育ち、星を眺めることで自分を慰めることしか知らない青年にとって、伯爵夫人は生涯、忘れることのできない人となっていくんですね。
昔、これを読んだときにわたしの胸板を突き破った衝撃の大きさは、わたし自身のあり方にあったでしょうか。どんな努力にもかかわらず、ことがうまくいかないとき、周囲のだれにも目を向けてもらえないようなとき、思惑がいつも外れるとき、才能や実力の真価をどこにも発揮できないようなとき、自分のことばが相手にどうしても届かないとき、胸のなかにある思想がだれにも評価されないようなとき…。
そう、このごろ折あるごとに考えているギリシア神話のほうから言うと、タンタロスのような状態にあるとき、フェリックスは深い孤独と疲弊感と劣等意識のなかで崇高なこころに出会ったんですね。タンタロスというのは、ゼウスの子で、黄泉の国の湖にあって、顎のところまで水に浸されながら、焼けつくようなノドの渇きを癒すことができないでいる哀れな存在。ヘラクレスが12の難行と戦っているとき、スティクス川を渡ったハデスの国(黄泉の国)で目にした凄まじい光景で、水を飲もうとするとサ―ッと水は退き、木の実を摘もうとするとピイーンと枝が退き、永遠の飢渇に苦しみつつなお生きていかなければならない男。ツキに見放されたおれって、まるでタンタロスだ、とまいってしまっていたときに出会った気高い女神。アンリエッタは、フェリックス(あるいは、わたし)には、そんなふうに見えたものです。つまり、人生の暗い谷間の底のようなところから見えた、あまりにも神々しい太陽、匂いやさしい大輪の花。
『ゴリオ爺さん』を読んだときに調べたことによりますと、ふたりの子持ちと書かれているモルソフ夫人のモデルと思われるベルニー夫人は、当時(バルザック23歳)、45歳、9児の母親でした。バルザックはパリの屋根裏部屋にこもって作家修行をしているときで、まだ誰にも評価されていませんでした。で、ベルニー夫人とその近親者たちに資金を出してもらって、バルザックは自分で出版業をはじめます。もちろん、商売はうまくいきません。その間にも、高級娼婦オランプ・ペリシエやカストリ公爵夫人との関係が生じ、そのつど破局します。ポーランドのハンスカ夫人や、バルザックの子をなすことになるマリア・デュ・フレネーとの関係、私生児をなすギドボニ・ヴィスコンチ伯爵夫人…と、まことにおさかんです。それでも、36歳、再びベルニー夫人との交際がはじまり、その息子の死を機にふたりの関係は終局を迎えます。
『谷間の百合』は壮大な恋愛小説として読まれるのが普通ですが、肉と霊の葛藤のなかで展開する崇高な愛の行方もさることながら、自然をうつすバルザックの筆力の冴えと、人間を観察するその目の鋭く澄んでいることが印象に深く刻まれる作品でしたね。
いまのわたしは、8月中旬まで、地域のさまざまなことに追われて本を読む時間がほとんどなく、それが大きな悩みです。ピンチです。そんななか、Pwm さんとこうした感動を共有できることを、ほんとうにありがたいと思っています。
こころの闇に咲く清純な大輪の花、崇高な愛のすがた
「谷間の百合」やっと読み終えました。「ゴリオ爺さん」のパリの社交界とは正反対の息苦しいほどの清い愛。モルソフ夫人の心の葛藤。そして愛に死ぬ衝撃。パリの社交界での成功のレールを引く夫人。そこに世俗的な愛が忍び寄ることを恐れながらも愛するフェリックスをパリに送り出す気持ちを思うと、それほどまでに深い愛だったのだと最後に気付きます。読みにくいと思いながらも惹かれるバルザックの作品です。〔Pwm さん〕
----------------------------
すごい! さすが、ですね。バルザックの名を知らない人はなくても、いまどきこの大河小説をひもとこうなんて人は、めったにいません。読書をよくするとされるみなさんのなかでも、最近『谷間の百合』や『ゴリオ爺さん』『従妹ベット』といったあたりを読んだという人は、たぶんいないはず。薄っぺらなもののうえで幼児顔して滑っているだけでなく、こういうものをじっくり読んでいただきたいですがね。だって、こういうものを読んだあとには、自分が新しくなったような、自分がひとつ確かに高められたような、そんな悦びがありますよね。新書などで表面的なその場限りの簡易知識をいくら詰め込んでもぜったいに得ることのできない、感動の深さがここにはあります。うわっ面の知識を追うことのむなしさを知るときでもあります。
『谷間の百合』――。もうずいぶん前に読んだもので、忘れてしまったことばかりですが、そうそう、バルザック自身を想わせる主人公のフェリックス。百合の花に譬えられる美しい貴婦人モルソフ夫人(アンリエット)。ふたりはある舞踏会で偶然に出会い、青年は踊ったあと思わず夫人の匂やかな肩に顔をうずめてキスをしてしまいます。愛情薄い家庭で育ち、星を眺めることで自分を慰めることしか知らない青年にとって、伯爵夫人は生涯、忘れることのできない人となっていくんですね。
昔、これを読んだときにわたしの胸板を突き破った衝撃の大きさは、わたし自身のあり方にあったでしょうか。どんな努力にもかかわらず、ことがうまくいかないとき、周囲のだれにも目を向けてもらえないようなとき、思惑がいつも外れるとき、才能や実力の真価をどこにも発揮できないようなとき、自分のことばが相手にどうしても届かないとき、胸のなかにある思想がだれにも評価されないようなとき…。
そう、このごろ折あるごとに考えているギリシア神話のほうから言うと、タンタロスのような状態にあるとき、フェリックスは深い孤独と疲弊感と劣等意識のなかで崇高なこころに出会ったんですね。タンタロスというのは、ゼウスの子で、黄泉の国の湖にあって、顎のところまで水に浸されながら、焼けつくようなノドの渇きを癒すことができないでいる哀れな存在。ヘラクレスが12の難行と戦っているとき、スティクス川を渡ったハデスの国(黄泉の国)で目にした凄まじい光景で、水を飲もうとするとサ―ッと水は退き、木の実を摘もうとするとピイーンと枝が退き、永遠の飢渇に苦しみつつなお生きていかなければならない男。ツキに見放されたおれって、まるでタンタロスだ、とまいってしまっていたときに出会った気高い女神。アンリエッタは、フェリックス(あるいは、わたし)には、そんなふうに見えたものです。つまり、人生の暗い谷間の底のようなところから見えた、あまりにも神々しい太陽、匂いやさしい大輪の花。
『ゴリオ爺さん』を読んだときに調べたことによりますと、ふたりの子持ちと書かれているモルソフ夫人のモデルと思われるベルニー夫人は、当時(バルザック23歳)、45歳、9児の母親でした。バルザックはパリの屋根裏部屋にこもって作家修行をしているときで、まだ誰にも評価されていませんでした。で、ベルニー夫人とその近親者たちに資金を出してもらって、バルザックは自分で出版業をはじめます。もちろん、商売はうまくいきません。その間にも、高級娼婦オランプ・ペリシエやカストリ公爵夫人との関係が生じ、そのつど破局します。ポーランドのハンスカ夫人や、バルザックの子をなすことになるマリア・デュ・フレネーとの関係、私生児をなすギドボニ・ヴィスコンチ伯爵夫人…と、まことにおさかんです。それでも、36歳、再びベルニー夫人との交際がはじまり、その息子の死を機にふたりの関係は終局を迎えます。
『谷間の百合』は壮大な恋愛小説として読まれるのが普通ですが、肉と霊の葛藤のなかで展開する崇高な愛の行方もさることながら、自然をうつすバルザックの筆力の冴えと、人間を観察するその目の鋭く澄んでいることが印象に深く刻まれる作品でしたね。
いまのわたしは、8月中旬まで、地域のさまざまなことに追われて本を読む時間がほとんどなく、それが大きな悩みです。ピンチです。そんななか、Pwm さんとこうした感動を共有できることを、ほんとうにありがたいと思っています。
Posted by 〔がの〕さん at 16:11│Comments(0)
│名作鑑賞〔海外〕