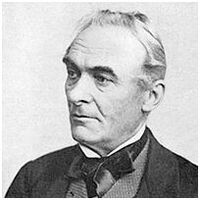2022年12月13日
F/ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンソン
ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンソン

ペルソナ(蔭、仮面)と折り合いをつけつつ
“ジキルとハイド”といえば「二重人格」「多重人格」の代名詞のようにして人口に膾炙されている。だれもが知っているようでいて意外に知られていないのがその物語であり、その概念。ひとのこころの二面性を象徴的に描きだした怪奇SFの古典とされるこの傑作。蔭(ペルソナ/仮面)を持つことなく生きるこみとは難しく、どんなひとのこころにも巣くうもうひとつの邪悪な心情をみごとに抉りだしている。さあ、ジキルとは何ものか、ハイドとは何ものか、作者ロバート・スティーヴンソン(英・1850~1894)はこの作品を通じて何をいいたかったのか、いっしょに探ってみよう。慈善家であり敬虔な信仰家、正直にして古典的な紳士であるジーキル博士の家に、いつのころからか、ハイドと名乗る醜悪な容貌の、小柄な男が出入りするようになる。そして非道な殺人事件が発生。この怪奇な事件とジーキル博士の秘密を追うのが弁護士のアスタン。主要な登場人物を見てみよう。
●ヘンリー・ジーキル・・・努力と徳行と節制の生活を送る、医学・法学の博士号をもつ高潔な紳士。地位と名誉ある、温和にして善良な市民だったが、座敷牢のような禁断の実験室に閉じこもって、ひとと会わないで秘事に没頭する。無味乾燥な学究生活に対する嫌気がつのる。時には徳性を捨てて逸楽に耽りたいという気持ちとの葛藤。未知の精神の自由感への憧れと誘惑のままに……。
●エドワード・ハイド・・・会うひとをぞっとさせる醜悪な容貌の小男。変態的で畸形の印象の男。殺人事件まで引き起こす冷酷にして凶暴、悪逆非道の権化としての悪鬼、純粋な悪の化身である。自己中心的であり、他者を苦しめることに獣のように貪欲。木石のごとき道徳的不感症と悪行へと猪突する兇暴性を発揮するミスター・ハイド隠れ役。
●ガブリエル・ジョン・アスタン・・・ロンドンに事務所をかまえる弁護士。ひとり暮らしをしている。ひょろひょろノッポで陰気くさく、口数少なく吃音の傾向もある。笑顔など見せたことはない、それでいて人情味ゆたか。ジーキル博士やラニョン医師の友人。ジーキル博士の常軌を逸した遺言書――死亡または失踪した場合には全財産をハイド氏にゆずる、という――を預かっている。隠れ役を追うミスター・シーク。
●ラニョン・・・ジーキルとアスタンと同窓の旧くからの友人で、患者が殺到する名医である。ジーキルを訪ねてから1週間後に奇妙な病気で倒れ、2週間ももたずに死去。死の直前な書かれた手記で、一杯の薬液により旧友がその性格も容姿も違う別人に変わる光景を目の前にしたとする報告をしたためる。これによりジーキルの全容が明かされる。
◆非道な事件1.≪カルー殺害事件≫
深夜のロンドン。月光のなかで男に道を訊く白髪の老紳士、サー・ダンヴァズ・カルー上院議員。突然、怒りを爆発させる小男のハイド。「すっかり自制を失くして老紳士を地べたになぐり倒し、つぎの瞬間には兇暴な猿のように相手を足で踏みにじり、めちゃくちゃに殴りつける。そのため、骨は音を立てて砕け、死骸は路上に跳ねあがった。この凶行に使われたステッキは、かつてアスタンがジーキルに贈ったものだった。
◆非道な事件2.≪花売り少女殴打事件≫
夜の都会、街路灯の下で男と子どもが出会う。そのすれ違いざま、いきなり子どもを踏み倒し、その泣き声にも耳を貸すことなく立ち去っていく悪鬼。花を買ってもらおうとして近づいた貧しげな少女を、いきなり邪険になぐり倒して大けがをさせた醜い小男。

この作者のもっとも親しまれている作品『宝島』
海賊シルバーの悪逆非道ぶりは児童文学では珍しい
ジーキルの告白と作者の人間観
1.「公衆の面前では、世の人のあたたかい尊敬の重荷を背負ってこつこつと努力しながら、時あらば、……こんな借り物は思いきりよく脱ぎ捨ててしまって、まっ逆さまに放埓の大海に飛び込むこと」への誘惑に絶えず揺れ動かされている人間存在。
2.「次第しだいにわたし本来の善なる自己を喪失し、次第しだいにわたしの悪なる自己に合体しつつある」感覚へとのめりこんでいき、幻影に満ちた空想と、言われない瞋恚(しんい)に煮えかえって、放埓に、兇暴に、悪意に突っ走るもうひとりの自分。
⒊ 人間のもつ、抑えがたい享楽性。「人間はじつは単一の存在ではなくして、二元的な存在である」「究極のところ、一人ひとりが多種多様の、互いに調和しがたい個々独立の住民の集団のごときものに過ぎない」「人間は完全かつ本源的に二重性格のものである」「我われの出会うほどの人びとは、すべて善と悪との混合体である」高潔なだけでは社会に生きていけない人間。所詮は善と悪との混合体であるから、一方を排除するのではなく、正と負の両面を抱えながら、それをうまく共生させていくしかない、とする考え方。
4 「この一見まことに充実して見える肉体なるものが、じつは蜉蝣(かげろう)のごとく実体なきもの、狭霧のごとくはかないものであること」の認識。ひとつの認識の裏にはかならず別の心情、移ろいやすい心情が潜んでいるという作者。
☆ ☆
モラル正しいだけでは生きにくい。自分のなかに棲む醜い怪物が時を得て暴れだすことがある。きれいな玄関と床の間だけで生活していくことはできない。わたしたちのなかには、いつももう一人のわたし、影としてのペルソナが生きている。他人には知られたくないその負の部分とどう折り合いをつけていくか、そこをわれわれに問いかけている作品と言えないか。

ペルソナ(蔭、仮面)と折り合いをつけつつ
“ジキルとハイド”といえば「二重人格」「多重人格」の代名詞のようにして人口に膾炙されている。だれもが知っているようでいて意外に知られていないのがその物語であり、その概念。ひとのこころの二面性を象徴的に描きだした怪奇SFの古典とされるこの傑作。蔭(ペルソナ/仮面)を持つことなく生きるこみとは難しく、どんなひとのこころにも巣くうもうひとつの邪悪な心情をみごとに抉りだしている。さあ、ジキルとは何ものか、ハイドとは何ものか、作者ロバート・スティーヴンソン(英・1850~1894)はこの作品を通じて何をいいたかったのか、いっしょに探ってみよう。慈善家であり敬虔な信仰家、正直にして古典的な紳士であるジーキル博士の家に、いつのころからか、ハイドと名乗る醜悪な容貌の、小柄な男が出入りするようになる。そして非道な殺人事件が発生。この怪奇な事件とジーキル博士の秘密を追うのが弁護士のアスタン。主要な登場人物を見てみよう。
●ヘンリー・ジーキル・・・努力と徳行と節制の生活を送る、医学・法学の博士号をもつ高潔な紳士。地位と名誉ある、温和にして善良な市民だったが、座敷牢のような禁断の実験室に閉じこもって、ひとと会わないで秘事に没頭する。無味乾燥な学究生活に対する嫌気がつのる。時には徳性を捨てて逸楽に耽りたいという気持ちとの葛藤。未知の精神の自由感への憧れと誘惑のままに……。
●エドワード・ハイド・・・会うひとをぞっとさせる醜悪な容貌の小男。変態的で畸形の印象の男。殺人事件まで引き起こす冷酷にして凶暴、悪逆非道の権化としての悪鬼、純粋な悪の化身である。自己中心的であり、他者を苦しめることに獣のように貪欲。木石のごとき道徳的不感症と悪行へと猪突する兇暴性を発揮するミスター・ハイド隠れ役。
●ガブリエル・ジョン・アスタン・・・ロンドンに事務所をかまえる弁護士。ひとり暮らしをしている。ひょろひょろノッポで陰気くさく、口数少なく吃音の傾向もある。笑顔など見せたことはない、それでいて人情味ゆたか。ジーキル博士やラニョン医師の友人。ジーキル博士の常軌を逸した遺言書――死亡または失踪した場合には全財産をハイド氏にゆずる、という――を預かっている。隠れ役を追うミスター・シーク。
●ラニョン・・・ジーキルとアスタンと同窓の旧くからの友人で、患者が殺到する名医である。ジーキルを訪ねてから1週間後に奇妙な病気で倒れ、2週間ももたずに死去。死の直前な書かれた手記で、一杯の薬液により旧友がその性格も容姿も違う別人に変わる光景を目の前にしたとする報告をしたためる。これによりジーキルの全容が明かされる。
◆非道な事件1.≪カルー殺害事件≫
深夜のロンドン。月光のなかで男に道を訊く白髪の老紳士、サー・ダンヴァズ・カルー上院議員。突然、怒りを爆発させる小男のハイド。「すっかり自制を失くして老紳士を地べたになぐり倒し、つぎの瞬間には兇暴な猿のように相手を足で踏みにじり、めちゃくちゃに殴りつける。そのため、骨は音を立てて砕け、死骸は路上に跳ねあがった。この凶行に使われたステッキは、かつてアスタンがジーキルに贈ったものだった。
◆非道な事件2.≪花売り少女殴打事件≫
夜の都会、街路灯の下で男と子どもが出会う。そのすれ違いざま、いきなり子どもを踏み倒し、その泣き声にも耳を貸すことなく立ち去っていく悪鬼。花を買ってもらおうとして近づいた貧しげな少女を、いきなり邪険になぐり倒して大けがをさせた醜い小男。

この作者のもっとも親しまれている作品『宝島』
海賊シルバーの悪逆非道ぶりは児童文学では珍しい
ジーキルの告白と作者の人間観
1.「公衆の面前では、世の人のあたたかい尊敬の重荷を背負ってこつこつと努力しながら、時あらば、……こんな借り物は思いきりよく脱ぎ捨ててしまって、まっ逆さまに放埓の大海に飛び込むこと」への誘惑に絶えず揺れ動かされている人間存在。
2.「次第しだいにわたし本来の善なる自己を喪失し、次第しだいにわたしの悪なる自己に合体しつつある」感覚へとのめりこんでいき、幻影に満ちた空想と、言われない瞋恚(しんい)に煮えかえって、放埓に、兇暴に、悪意に突っ走るもうひとりの自分。
⒊ 人間のもつ、抑えがたい享楽性。「人間はじつは単一の存在ではなくして、二元的な存在である」「究極のところ、一人ひとりが多種多様の、互いに調和しがたい個々独立の住民の集団のごときものに過ぎない」「人間は完全かつ本源的に二重性格のものである」「我われの出会うほどの人びとは、すべて善と悪との混合体である」高潔なだけでは社会に生きていけない人間。所詮は善と悪との混合体であるから、一方を排除するのではなく、正と負の両面を抱えながら、それをうまく共生させていくしかない、とする考え方。
4 「この一見まことに充実して見える肉体なるものが、じつは蜉蝣(かげろう)のごとく実体なきもの、狭霧のごとくはかないものであること」の認識。ひとつの認識の裏にはかならず別の心情、移ろいやすい心情が潜んでいるという作者。
☆ ☆
モラル正しいだけでは生きにくい。自分のなかに棲む醜い怪物が時を得て暴れだすことがある。きれいな玄関と床の間だけで生活していくことはできない。わたしたちのなかには、いつももう一人のわたし、影としてのペルソナが生きている。他人には知られたくないその負の部分とどう折り合いをつけていくか、そこをわれわれに問いかけている作品と言えないか。
Posted by 〔がの〕さん at 18:28│Comments(0)
│名作鑑賞〔海外〕